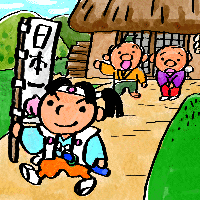桃太郎
桃 太郎
むかし 、 むかし 、 ある ところ に 、 お じいさん と おばあ さん が あり ました 。 まいにち 、 お じいさん は 山 へ しば刈り に 、 おばあ さん は 川 へ 洗濯 に 行き ました 。 ある 日 の 事 、 おばあ さん が 川 で 、 洗濯 を して い ます と 、 川上 から 大きな 桃 が 一 つ 、 ♪ ドンブラコッコ 、 スッコッコ ♪ ドンブラコッコ 、 スッコッコ と 、 流れて 来 ました 。 「 おや おや 、 これ は みごとな 桃 だ こと 。 お じいさん へ の お みやげ に 、 家 へ 持って 帰り ましょう 」 おばあ さん は 、 そう 言い ながら 、 腰 を かがめて 桃 を 取ろう と し ました が 、 桃 は 遠くて 手 が とどき ませ ん 。 そこ で 、 おばあ さん は 、 ♪ あっち の 水 は 、 か あらい ぞ 。 ♪ こっち の 水 は 、 ああ まい ぞ 。 ♪ か あらい 水 は 、 よけて 来い 。 ♪ ああ まい 水 に 、 よって 来い 。 と 、 歌い ながら 、 調子 よく 手 を たたき ました 。 すると 桃 は 、 ♪ ドンブラコッコ 、 スッコッコ ♪ ドンブラコッコ 、 スッコッコ と 、 おばあ さん の 前 へ 流れて 来 ました 。 おばあ さん は 、 にこにこ し ながら 桃 を 拾い 上げる と 、 「 さあ 、 早く お じいさん と 二 人 で 分けて 、 食べ ましょう 」 と 、 桃 を 洗濯物 と 一緒に たらい の 中 に 入れて 、 家 に 持って 帰り ました 。
夕方 に なる と 、 やっと お じいさん は 山 から しば を 背負って 帰って 来 ました 。 「 おばあ さん 、 今 帰った よ 」 「 おや 、 お じいさん 、 待って い ました よ 。 さあ 、 良い 物 が ある から 、 早く お 上が ん なさい 」 「 ほう 、 良い 物 と は 、 一体 何 だ ね 」 お じいさん が わらじ を ぬいで 家 に 入る と 、 おばあ さん は 戸棚 の 中 から さっき の 桃 を 持って きて 言い ました 。
「 ほら 、 大きな 桃 でしょう 」 「 ほ ほう 、 これ は これ は みごとな 桃 だ 。 これ は どうした の だ ? 」 「 今日 、 川 で 拾って 来た のです よ 」 「 桃 を 川 で 拾う と は 、 それ は めずらしい 」 「 では 、 さっそく 食べる と し ましょう 。 お じいさん 、 悪い です けど 、 桃 を 切って ください な 」 「 よし 、 わかった 」 お じいさん が そう 言って 、 包丁 で 桃 を 切ろう と する と 、 突然 桃 が ブルブル と 震えて 、 パカン と 二 つ に 割れ ました 。 そして 桃 の 中 から 、 「 お ぎ ゃあ ー 、 お ぎ ゃあ ー 」 と 、 かわいらしい 赤ちゃん が 、 元 気 良く 飛び出した のです 。 「 なんと ! 」 「 おや 、 まあ 」 お じいさん も おばあ さん も びっくり し ました が 、 おばあ さん は その 赤ちゃん を 大事 そうに 抱き上げて 言い ました 。 「 わたし たち が 、 いつも 子ども が ほしい と 言って いた から 、 きっと 神さま が この 子 を 授けて 下さった に ちがい あり ませ ん よ 」 「 ああ 、 きっと そう だ 」 お じいさん と おばあ さん は 、 すぐ に お 湯 を 沸かす と 、 洗濯物 を 入れる たらい に お 湯 を 入れて 、 さっそく 赤ちゃん を うぶ湯 に つから せ ました 。 すると 赤ちゃん は 気持ちよ さ そうに 笑う と 、 「 う ーー ん 」 と 、 大きく のび を した のです 。 する と その 赤ちゃん の 力 が とても 強くて 、 おばあ さん は ころん と 転んで しまい ました 。 「 おや おや 、 何と 元気 の いい 子 だろう 」 お じいさん と おばあ さん は 顔 を 見合わせる と 、 おかし そうに 笑い ました 。 そして この 赤ちゃん は 、 桃 の 中 から 生まれた 子 な ので 、『 桃 太郎 』 と 名付け られ ました 。
お じいさん と おばあ さん は 、 桃 太郎 を それはそれは 大事に 育て ました 。 赤ちゃん の 頃 から 力 の 強い 桃 太郎 は 、 成長 する に つれて どんどん 強く なり 、 まだ 子ども ながら 近所 の 村 々 で 桃 太郎 に すもう で 勝てる 者 は 大人 でも い ない ほど でした 。 でも 、 桃 太郎 は とても やさしい 子ども で 、 お じいさん と おばあ さん に とても 親孝行 を し ました 。
桃 太郎 も 、 ついに 十五 才 に なり ました 。 自分 でも 日本 一 力 が 強い と 思った 桃 太郎 は 、 いつか その 力 を みんな の 役 に 立て たい と 思う ように なり ました 。 そこ へ 、 あちこち を 旅 して 回る 旅人 から 、 桃 太郎 は こんな 話し を 聞いた のです 。 「 何 年 も 何 年 も 船 を こいで 行く と 、 遠い 海 の 果て に 『 鬼 ヶ 島 』 と いう ところ が ある 。 そこ に は 悪い 鬼 ども が 、 くろがね の お 城 に 住んで いて 、 あちこち の 国 から 奪って きた 宝物 を 守って いる そうだ 」 この 話し を 聞いた 桃 太郎 は 、 その 鬼 ヶ 島 へ 行って み たく なり 、 お じいさん と おばあ さん の 前 へ 出て 言い ました 。 「 どうか 、 わたし を 旅 に 出さ せて 下さい 」 お じいさん と おばあ さん は 、 びっくり です 。 「 旅 って 、 どこ へ 行く つもりだ 」 「 はい 、 鬼 ヶ 島 へ 行って 、 悪い 鬼 を せいばつ に 行こう と 思い ます 」 「 ほう 、 それ は いさましい 事 だ 」 「 そんな 遠方 へ 行く ので は 、 さぞ お腹 が 空く でしょう から 、 お 弁当 を こしらえて あげ ましょう 」 お じいさん も おばあ さん も 桃 太郎 の 強 さ を 知って い ました から 、 桃 太郎 が 鬼 ヶ 島 へ 行く の を 喜び ました 。 お じいさん と おばあ さん は 、 庭 の まん 中 に 大きな 臼 を 持ち出す と 、 「 ぺっ たん 、 ぺっ たん 、 ぺっ たん こ 。 ぺっ たん 、 ぺっ たん 、 ぺっ たん こ 」 と 、 お 弁当 の キビ 団子 を つき ました 。 そして 桃 太郎 は お じいさん が 用意 した お 侍 の 着る ような 陣羽織 ( じんばおり ) を 着て 、 刀 を 腰 に さして もう と 、 出来 上がった ばかりの キビ 団子 の 袋 を ぶら下げ ました 。 そして 桃 の 絵 の 描いて ある 軍 扇 も 作って もらい ました 。
「 では 、 お 父さん 、 お 母さん 、 鬼 ヶ 島 へ 鬼 退治 に 行って まいり ます 」 「 ああ 、 立派に 鬼 を 退治 して くる が いい 」 「 体 に 気 を つけて 、 けが を し ない ように ね 」 「 な に 、 大丈夫です よ 。 わたし に は 日本 一 の キビ 団子 が あり ます から 。 では 、 ごきげんよう 」 桃 太郎 は 元気な 声 を のこして 出て いき 、 お じいさん と おばあ さん は 、 桃 太郎 の 姿 が 見え なく なる まで 見送って い ました 。
さて 、 鬼 ヶ 島 へ 出発 した 桃 太郎 が ず ん ず ん 進んで 大きな 山 に 来る と 、 草むら の 中 から 、 「 ワン 、 ワン 」 と 、 一 匹 の イヌ が かけて 来 ました 。 桃 太郎 が 振り返る と 、 犬 は 桃 太郎 に ていねいに おじぎ を して 言い ました 。 「 桃 太郎 さん 、 桃 太郎 さん 。 どちら へ おい で に なり ます か ? 」 「 鬼 ヶ 島 へ 、 鬼 退治 に 行く の さ 」 「 それでは 、 わたし も お供 さ せて ください 」 「 よし 、 わかった 。 それでは 日本 一 の キビ 団子 を やる から ついて 来い 」 こうして 犬 は キビ 団子 を 一 つ もらって 、 桃 太郎 の お供 に 加わり ました 。
山 を 下りて しばらく する と 、 桃 太郎 と 犬 は 森 の 中 に 入り ました 。 すると 木 の 上 から 、 「 キィー 、 キィー 」 と 、 一 匹 の サル が 下りて 来 ました 。 桃 太郎 が 振り向く と 、 サル は 桃 太郎 に ていねいに おじぎ を して 言い ました 。 「 桃 太郎 さん 、 桃 太郎 さん 。 どちら へ おい で に なり ます か ? 」 「 鬼 ヶ 島 へ 、 鬼 退治 に 行く の さ 」 「 それでは 、 わたし も お供 さ せて ください 」 「 よし 、 わかった 。 それでは 日本 一 の キビ 団子 を やる から ついて 来い 」 こうして サル も キビ 団子 を 一 つ もらって 、 桃 太郎 の お供 に 加わり ました 。
森 を 抜けて しばらく する と 、 桃 太郎 と 犬 と サル は 広い 野原 へ 出 ました 。 すると 空 の 上 から 、 「 ケン 、 ケン 」 と 、 一 羽 の キジ が 鳴き ながら 降りて 来 ました 。 桃 太郎 が 振り向く と 、 キジ は 桃 太郎 に ていねいに おじぎ を して 言い ました 。 「 桃 太郎 さん 、 桃 太郎 さん 。 どちら へ おい で に なり ます か ? 」 「 鬼 ヶ 島 へ 、 鬼 退治 に 行く の さ 」 「 それでは 、 わたし も お供 さ せて ください 」 「 よし 、 わかった 。 それでは 日本 一 の キビ 団子 を やる から ついて 来い 」 こうして キジ も キビ 団子 を 一 つ もらって 、 桃 太郎 の お供 に 加わり ました 。
桃 太郎 が 犬 と サル と キジ の 三 匹 の 家来 を 連れて 、 ず ん ず ん 進んで 行く と 、 やがて 広い 海 に 出 ました 。 近く に ちょうど 船 が あった ので 、 桃 太郎 と 、 三 匹 の 家来 は さっそく 船 に 乗り 込み ました 。 「 桃 太郎 さん 、 わたし が 船 を こぎ ましょう 」 犬 は そう 言う と 、 船 を こぎ 出し ました 。 「 桃 太郎 さん 、 わたし が かじ取り を し ましょう 」 サル は そう 言う と 、 かじ に 座り ました 。 「 桃 太郎 さん 、 わたし が 物見 ( ものみ ) を し ましょう 」 キジ は そう 言う と 、 船 の へさき に 立ち ました 。
しばらく は 良い お 天気 で 、 海 に は 波 一 つ あり ませ ん でした が 、 しばらく する と 風 が 出て きて 、 稲妻 が 走り ました 。 「 あの 稲妻 の 方角 に 、 鬼 ヶ 島 が ある に 違いない 。 犬 よ 、 サル よ 、 あっち に 向かって くれ 」 桃 太郎 が 言う と 、 犬 と サル は 稲妻 が 走った 方 へ 船 を 走ら せ ました 。 する と 、 へさき に 立って 物見 を して いた キジ が 言い ました 。 「 桃 太郎 さん 、 あそこ に 島 が 」
「 おおっ 、 確かに 島 だ 。 鬼 ヶ 島 に 違いない 」 やがて 島 に 近づく と 、 大岩 の 上 に 建って いる 鬼 の お 城 が 見え ました 。 その お 城 の 門 の 前 に は 、 見張り を して いる 鬼 の 兵隊 の 姿 も 見え ます 。 桃 太郎 一行 は 、 鬼 ヶ 島 に やって 来た のです 。
「 キジ よ 、 お前 は 空 を 飛んで 、 先 に 鬼 の 城 へ 行って くれ 」 桃 太郎 は そう 言う と 、 犬 と サル を したがえて 鬼 ヶ 島 に 上陸 し ました 。 見張り を して いた 鬼 の 兵隊 たち は 、 桃 太郎 の 姿 を 見る と 、 びっくり して 、 あわてて お 城 の 門 の 中 に 逃げ 込んで 、 鉄 の 門 を 固く 閉め ました 。 すると 犬 が 鉄 の 門 の 前 に 立って 、 門 を ドンドン と 叩き ながら 言い ました 。 「 日本 一 の 桃 太郎 さん が 、 お前 たち を せい ばい に おい で に なった のだ ぞ 。 ここ を 開けろ ! 」 それ を 聞いて 、 鬼 たち が 震え 上がり ます 。 「 桃 太郎 だって ! 」 「 桃 太郎 と 言えば 、 日本 一 の 強者 ( こわ もの → 強い 人 ) だ ぞ 。 絶対 に 中 へ 入れる な 」 鬼 たち は 一生懸命に 、 鉄 の 門 を 押さえ ました 。 この 鉄 の 門 は 、 さすが の 桃 太郎 でも 壊す こと が 出来 ませ ん 。 すると 先 に 飛んで いった キジ が 空 から 下りて きて 、 門 を 押さえて いる 鬼 たち の 目 を 突き 回り ました 。 「 わ あ 、 何 だ 、 この キジ は 」 鬼 たち が 頭 を 押さえて 逃げ 出す と 、 サル が するする と 高い 鉄 の 門 を よじ登って 行き 、 内側 から 門 を 開け ました 。 「 それ 、 行く ぞ ! 」 桃 太郎 は 声 を 上げる と 、 三 匹 の 家来 たち と 一緒に 鬼 の お 城 に 攻め 入り ました 。 お 城 の 中 から は 、 鬼 の 親分 が 大勢 の 家来 を 引き連れて 現れ ました 。 鬼 たち は 太い 鉄 の 棒 を 振り 回し ながら 桃 太郎 に 襲い かかり ます が 、 キジ が 空 から 鬼 の 目 を 突き 、 犬 が 鬼 の 向う ず ね に かみつき 、 サル が 鬼 の 体 に 飛び乗って 顔 を 引っかき 、 桃 太郎 が 自慢 の 力 で 鬼 を 投げ飛ばし ます 。 こうして 桃 太郎 一行 は 鬼 を 次々 と 倒して 、 最後に 残った 鬼 の 親分 を 桃 太郎 が 地面 に 押し倒し ました 。 「 どう だ 、 これ でも 降参 し ない か 」 すると 鬼 の 親分 は 、 大粒の 涙 を ポロポロ こぼし ながら 言い ました 。 「 桃 太郎 さん 、 降参 し ます から 、 命 だけ は お 助け 下さい 。 その代わり に 、 今 まで 集めた 宝物 を 残らず 差し上げ ます から 」 「 よし 、 ならば 助けて やろう 」
鬼 の 親分 は 約束 通り 、 お 城 から たくさんの 宝物 を 持って き ました 。 それ は 、 身 に つける と 姿 が 消える 『 隠れみの 』 に 『 隠れ が さ 』。 欲しい 物 を 出して くれる 『 うち で の 小づち 』 と 、 願い を かなえて くれる 『 如意 宝珠 ( にょい ほう じゅ → 願い を かなえて くれる 玉 )』。 その他 に も 『 珊瑚 ( さんご )』 や 『 たい まい (→ 海亀 の 甲羅 )』 や 『 瑠璃 ( るり → 青色 の 宝石 )』 など 、 高価な 宝物 を 山 の 様 に 車 に 積んで 差し出し ました 。 桃 太郎 は その 宝物 を 残らず 船 に 積む と 、 「 もう 二度と 、 悪い 事 を する で ない ぞ 」 と 、 鬼 たち に 言いつけて 、 日本 へ と 帰って 行き ました 。
さて 、 桃 太郎 の 村 で は 、 お じいさん と おばあ さん が 毎日 毎日 桃 太郎 の 帰り を 首 を 長く して 待って い ました 。 「 もう そろそろ 、 桃 太郎 が 帰って きて も いい ころ だ が 」 「 そう です ね 。 けが を して い なければ いい です けど 」 そこ へ 、 たくさんの 宝物 を 積んだ 車 を 引いて 、 桃 太郎 一行 が 帰って きた のです 。 お じいさん と おばあ さん は 大喜びです 。 桃 太郎 から 鬼 退治 の 話し を 聞いて 、 お じいさん と おばあ さん が 言い ました 。 「 えらい ぞ 、 えらい ぞ ! それ で こそ 日本 一 だ 」 「 まあ 、 まあ 、 けが が なく って 、 何より です 」
やがて 桃 太郎 は 鬼 ヶ 島 から 持ち帰った 宝物 を 一つ一つ 持ち主 の ところ へ 届けて やり 、 鬼 ヶ 島 で の 鬼 退治 の 話し を 世界 中 に 広めた と いう 事 です 。
おしまい